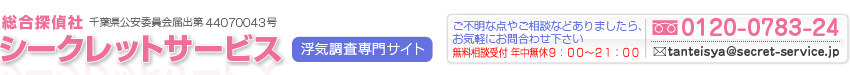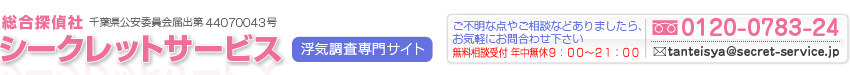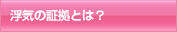















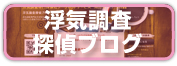

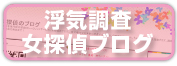



浮気以外の調査について
はコチラのサイトへどうぞ
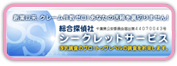







顧問弁護士


以下の決済がご利用出来ます






|

|
 1、財産分与とは
1、財産分与とは
離婚をする場合、夫婦の一方は相手に対して、財産を分け与えるよう請求できます。
当事者間で 離婚協議が成立しない時、又は離婚協議ができない時、当事者は家庭裁判所に離婚調停を申立てることが出来ます。
| 特有財産 | 結婚前からある財産。結婚中に相続・贈与等で自己名義にて得た財産。この特有財産は財産分与の対象外となります。 |
| 共有財産 | 結婚中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具什器。夫婦のいずれに属するか明かでない財産。この共有財産は財産分与の対象となります。 |
| 実質的共有財産 | 婚姻中、夫婦が協力して取得したが夫単独名義となっている不動産、有価証券(株券、国債等、ゴルフ会員権)、貯蓄、車等。この実質的共有財産は財産分与の対象となります。 |
共有財産の分与の割合は、原則は夫婦で半々となります。
2、退職金・社内預金・生命保険・住宅ローン返済分も分与対象
退職金・社内預金・生命保険・住宅ローン返済分も分与対象ですから、忘れずに計算・交渉します。退職金の分与に関しては、通常退職前5年以内に離婚する場合に分与の対象となるケースが多いようです。忘れてはいけないことは、財産を夫婦で負債(住宅ローン等)に関しても夫婦で分与することになります。
3、離婚による厚生年金の分割制度
2008年4月より、定年退職後の厚生年金に関して分割される制度ができました。
よって老後の生活が不安な為に離婚を我慢してきた方々も離婚に踏み切る為、近年では一気に離婚の件数が増加しています。
妻が厚生年金受給権の任意分割を受ける条件―
1 2007年4月1日以降に成立した離婚
2 配偶者が婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間がある
3 夫婦間で分割割合の合意がある。専業主婦が受ける分割の最大値は50%
4 専業主婦が2008年4月1日以降に離婚する場合、2008年4月1日~離婚 の第3号被保険者期間分は自動的に1/2に強制分割
5 請求手続きは離婚後2年以内
6 合意ができない場合は家庭裁判所にて調停
4、財産分与・慰謝料の税金
給付側に対する税金・財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合、給付者に対する税金はありません。
但し、不動産の分与で支払われる場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。
給付を受ける側に対する税金
財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合、被給付者に対する税金(贈与税、所得税)はない。これは贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
財産分与・慰謝料等が不動産の分与で支払われる場合、給付を受ける側に不動産取得税が課税されます。
不動産を分与する場合、税務署に行き事前に譲渡所得税その他の税額を確認しておくようにしましょう。
5、財産分与の時効は2年
離婚後に請求する場合、時効は離婚から2年。財産分与は離婚前に決めるようにしましょう。

 養育費の相場
養育費の相場
慰謝料と同様に養育費に決まった金額はありません。
子供一人に対して10万円欲しいと思う方、また実際に10万円支払う方もいます。
しかし現実ではそこまでの金額は非常に難しくなっており、支払う側の収入や生活状況、借金の金額等が考慮されます。
また支払われる側の収入や生活状況によっても大きく上下します。
 子供が幼児期に離婚する場合は小学校や中学校が私立か公立かも未確定であり、高校や大学、大学院も当然未確定です。
子供が幼児期に離婚する場合は小学校や中学校が私立か公立かも未確定であり、高校や大学、大学院も当然未確定です。
過去に多いケースを紹介しますと、義務教育が終了するまでは月々○万円。以降高校に入学したら月々○万円。高校卒業後社会人になった場合は終了。
但し、大学や専門学校に進学する可能性が高くなっている現在、大学卒業後までしっかりと取り決めることをお勧めします。
尚、物価の変動や支払う側の収入の変動、また支払われる側の生活状況の変化(再婚等)も考えられますので、そのような時の内容も取り決める必要があります。
一般的な平均金額は、義務教育終了まで子供一人の場合は3万円、二人の場合は5万円前後が多くなっているようです。
公正証書の作成
養育費の取り決めで争いになるケースは少ないようですが、大切なことは取り決め通り最後までしっかりと支払いをさせることです。
口約束や簡単な書面で済ませてしまった場合、約80%のケースが途中で支払いが滞っているのが現実です。
その為、金銭に関することは慰謝料や財産分与と同様に、必ず公正証書を作成するようにしましょう。

|